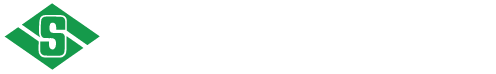梱包設計と包装の違いは?梱包の役割や梱包設計の流れを解説
2025年05月01日
自社商品の企画開発、作成時には梱包についての知識も必要です。一方で「梱包と包装の違いがイマイチ分からない」「梱包設計を行う流れが分からない」など、さまざまな悩みがあるかもしれません。
そこでこの記事では、梱包の役割や梱包設計を行うまでの流れを解説します。梱包と包装の違いについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

梱包とは、輸送を目的に物を包むことです。JIS規格では、梱包を「輸送を目的とした木製容器、鋼製容器、段ボール製容器などによる包装。荷造りと呼ぶこともある。」と定義しています。
輸送時や保管時に、物を保護する目的で使用されるダンボールや緩衝材などの資材は、梱包資材と呼ばれています。
包装と梱包、いずれも物を包むことは共通していますが、包装はある目的のために物を包む作業や技術、包んだ物の状態そのものを指します。
つまり、包装は梱包よりも包括的な言葉で、梱包も包装の一種に含まれます。
JIS規格では、包装を「物品の輸送、保管、取引、使用などに当たって、その価値及び状態を維持するための適切な材料、容器、それらに物品を収納する作業並びにそれらを施す技術又は施した状態」と定義しています。
さらに、包装の中でも「物品を中間業者に配送すること、及び/又は保管することを主目的として施す包装」を工業包装、「商品の一部として又は商品をまとめて取り扱うために、商業取引の各レベルに合わせて施す包装」を商業包装と定義して区別しています。
物の保護のほか、見栄えをよくするために使用するラッピングやリボン、シールなどの資材は、包装資材と呼ばれています。

梱包は製品を保管や輸送し、市場に流通させるために必要な作業です。梱包の持つ主な役割を順に解説します。
製品を梱包することで、利便性の向上につながります。多くの製品を輸送する際に、梱包により製品のサイズや形状を均一化することで、仕分けや積載時に持ち運びやすくなり、作業の効率が上がります。
製品を受け取ったほうも、持ち運びしやすくなったりそのまま保管しやすかったりと、多くのメリットを得られます。
梱包のもっとも大きな役割が、製品の破損を防ぐことです。輸送時、トラックが走っているときの振動や、荷卸し時や仕分け時に落下させてしまったときでも、緩衝材やダンボールで梱包することで製品を衝撃から守り、破損を防げます。
ほかにも製品の保管時、高温やニオイ、湿気、虫など製品の品質変化や劣化を招くものから製品を守るために、梱包が行われています。消費者へ製品の品質や規格を保ったまま届ける上で、梱包は大きな役割を担っています。
|
梱包の種類 |
特徴 |
|
ダンボール梱包 |
・頑丈で使い勝手がよい、一般的な梱包材 ・一般的なダンボールのほか、より強度を高めた二重ダンボール、三重ダンボールなども利用されている ・素材が紙のため水ぬれに弱い |
|
木箱梱包 |
・木の板で作られた箱型の梱包 ・木の板を網目状に組んだ「すかし箱」、木の板で全体を覆った「密閉箱」などの種類がある ・木箱には、重量200kg以下の物の梱包に使われるⅠ型、重量1.5tまでの物の梱包に使われるⅡ型の規格がある ・1.5t超の物を包む場合には、規格外の特注の木箱が必要 |
|
スキッド梱包 |
・木材やスチールなどで作られた腰下(スキッド)の上に物を置き、固定する梱包方法 ・物の周辺は覆わないため、物が露出している状態になる ・一般的には、コンテナ1個を使用する大型の物の梱包として使用されている |
|
スチール梱包 |
・木の代わりにスチールを用いた梱包方法 ・耐久性が高い ・木箱と異なり一定の規格がない ・一度作成すると形や大きさが調整できない |
|
パレット梱包 |
・梱包された物をパレットの上に積み上げ、輸送中に荷崩れしないよう全体を固定する梱包方法 ・荷台となるパレットに設けた薄い隙間に、フォークリフトの爪を通して荷物の積み下ろしを行う |
|
バリア梱包 |
・防水性に優れたアルミ製の素材で荷物を覆う梱包方法 ・サビの発生を防げる ・輸出用の梱包方法として多く用いられている |
包装はパッケージデザインから商品名、使用方法、成分、注意書きなどの情報を伝える役割を持っていますが、梱包も同様です。ダンボールやパレットに割れ物注意や天地無用、冷蔵保存などの記載をすることで、輸送時や保管時に適切な取り扱いができます。
梱包により製品のサイズや形状の均一化をすることで、輸送や保管時の製品の取り扱いが効率化し、積載や保管スペースの削減にもつながります。その結果作業による人件費や、輸送費、保管費のコスト削減も実現できるでしょう。製品を梱包によって保護することで、輸送時の破損や紛失といったトラブルも防げるため、再発送や再配達で発生するコストも抑えられます。

製品の流通過程を最適化するために、梱包設計により製品に合った梱包仕様を決めます。梱包設計では、製品の保護をはじめとした機能性を発揮するのはもちろん、梱包材のコストなども考慮し、設計していきます。
目的に合わせた梱包を設計するために、まず梱包目的を設定します。主な梱包目的には、以下のものがあります。
例えば製品の保護が梱包の目的なら、製品のサイズや形状、性質などを踏まえて、最適な梱包材の材質やサイズなどを選定していきます。
梱包設計を外注する場合は、梱包目的と要望、さらにコストやスケジュール、梱包の品質などを綿密に伝えた上で、設計の提案を受けることになります。
実際の梱包構造の設計を行います。梱包構造は、材料力学や構造力学に基づいた設計を行うために、CADや解析ソフトを使用することも一般的です。品質のほか、梱包の作業性や緩衝性も踏まえた上で、最適な梱包設計を行います。
梱包構造の設計をもとに、試作品(サンプル)を作成します。
作成した試作品に、各検査やテストを行います。社内でのデザインレビューのほか、落下や振動、圧縮などの各種規格に対応した包装貨物試験を実施し、安全性や耐久性に問題がないかを確認します。梱包そのものの安全性や品質のほか、コストや環境負荷などの面からも総合的に評価を行います。
試作品の作成と各種検査、テストを問題なくクリアしたら、梱包材の製造に入ります。検査やテストの基準を満たした試作品の量産を行い、梱包材として投入されます。
梱包設計は梱包の目的に合致した設計を行うことが重要です。適切な梱包設計によって、製品の破損を防げるだけでなく業務効率やコスト効率の改善が実現します。